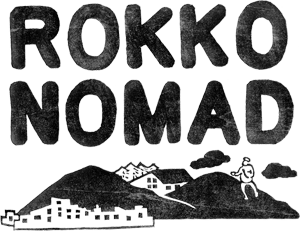ロコノマドからのお知らせやコラムを紹介しています。
六甲山で暮らすリアル Vol. 7 働き方を変えずに、靴型紙のワークスペースと家族の暮らしを六甲山へ。

ROKKONOMADの一画にある神戸の街と海を見下ろせるウッドテラスに面した部屋が、靴型紙の工房を営む「design room bluetip」松本健一さんの仕事場です。ここに仕事場を移し、六甲山のマンションに自宅を移したのは、2025年の春のこと。初めての山暮らしと、山での働き方を伺いました。
「都市の山」だからこそ、働き方をそのままに
――六甲山に職住を移したのは、子どもの学校選びがきかっけだと聞きました。
松本:六甲山小学校に通わせたいというのが先にあって、校区になる六甲山町に移りました。妻が子どもの教育環境を調べるなかで、全国にいろいろな面白い学校があると知って、六甲山小学校もそのひとつだったんです。もともと住んでいた垂水区の小学校だと1000人規模の学校だったので、それよりも1クラス10人の小規模クラスでみんなが顔を知っている関係性のなかで学べる環境がいいなと思って決めました。もちろん自然に囲まれて6年間を過ごせることも魅力でしたが、「山が好きで、自然が好きで」というわけではなくて。僕はトレッキングもしたことがないくらいです。よく、友だちにも森のなかの大きな保養所か別荘を買ったように誤解されるんですが、探せば意外と程よいマンションも幾つかありました。なので、家も小学校から5分のところにあるマンションです。

――仕事も生活も環境を変えることに、ためらいは?
松本:僕も妻も自分たちが面白いと思うほうに行ったらいいんじゃない、という気持ちでした。実際にまだ垂水区の家も残していて、完全に引越しをしたわけではないんです。徐々に荷物を上げていっているというか、まだ引越の途中というか。二拠点生活ですね。もしかしたら、いずれ垂水区の家は賃貸に貸し出すかもしれませんが、ときどき山を下りて垂水の家にもいます。仕事については、妻も長田で同じ靴関係の仕事をしています。ケーブルとバス、電車を乗り継いだら、今までとそんなに時間の違いもなく通勤できると思いました。僕は、基本的に工房で仕事をするので、シミュレーションしたところ場所さえ見つかれば何の問題もなかったです。


松本:業界的にオンラインよりも対面打ち合わせが常なので週に一度、大阪の取引先に行く必要がありますが、車で15分ほど六甲山を下りた後はすぐに高速に乗れて、垂水区から大阪に行くのとさほど差がないんです。裏六甲から行けば、須磨や垂水にも近いですし、宝塚、京都方面にもつながっているので、六甲山を拠点にしてどこにでも行きやすいです。やっぱり「都市の山」というのが大きくて、車があればそれほど不便じゃないと思いますね。

シェアオフィスの一画を、ワークスペースに
――実際、六甲山でどのように仕事をされているのですか?
松本:靴の型紙をつくる仕事です。靴のパーツを平面に起こして型紙をつくります。靴工場やメーカーさんと契約して毎月4〜5足分の型紙を届けています。実は、六甲山に住むことを決めたときは、六甲道駅付近でミシンが使える物件を借りて仕事をしようと考えていました。でも、六甲山にもシェアオフィスがあることを教えていただいて、ふらっとROKKONOMADを訪ねてみると、ちょうど部屋が空いていたんですよ。

松本:音の出るミシンも使える環境だったので借りることにして。仕事場を家から10分もかからないところに持てたのは良かったです。子どもの学校のお迎えにも行きやすいですしね。部屋は間取りが3つに区切れて、デスク室、ミシン室、資料室というように使いわけています。照明が間接照明で暗めだったのを白色電灯に変えた以外は、手を加えなくても仕事にぴったりな部屋でした。目の前がテラスで風も通りますし、言うまでもなく毎日が絶景です。

――自然に囲まれた山の上で働くことで何か良い変化はありますか?
松本:街で仕事していると、仕事の来訪者があったり、休憩がてら寄ってもらったりすることも多かったので、山の上になって顔を見る機会が減ったので少し寂しいですが、その分仕事に集中しています(笑)それに、息抜きしたくなったらテラスに出れば、気持ちのいい景色が観られて、澄んだ空気を吸えますしね。4月くらいから毎週、山の景色が変わっていきます。5月はツツジ、6月は紫陽花とか、咲く花も変わっていきます。


松本:家と仕事場が近くなったから、子どももよくここに遊びに来て、ROKKONOMADのスタッフさんとも仲良くなっています。仕事よりも、子どもへの影響のほうが大きいかも知れませんね。同じマンションの子どもと森の木にハンモックを張って遊んだり、六甲山ビジターセンターの展望台の芝生でバトミントンをしたりと、のびのび暮らせていますし、さっき言った季節の変化なんかも親が言わなくても自然と興味を持ってくれて、見つけた草花を植物図鑑で調べて名前がわかったものに付箋を貼り始めました。

――小学校の放課後はどう過ごしていますか?
松本:月曜と火曜には「山の子会」というこどもの居場所を保護者有志の方が運営されていて、六甲ケーブルの近くにある地域福祉センターに行っています。17時前に仕事場から車で迎えに行っています。木曜は山の上に住んでいる子ども同士で遊ぶことも多いですね。
――「山の子会」ではどんなことが?
松本:月曜は、書道や英語といった保護者の方が得意としていることを教えてもらう時間が多いです。火曜はケーブルで小学校に通っている子どもたちも集まってきて、宿題をやった後に、外遊びや畑の土いじりなど。おにぎりやおやつも出してくださいます。

山にある面白い場所や人とつながる
――これから六甲山でやってみたいことがありますか?
松本:DIYはやってみたいです。今はまだ時間がなくてやれていないんですけど、工房のちょっとした物とかを自分で作れたらいいですね。近所の方と話していたら、「丸ノコとか何か必要な道具があったら貸してあげるよ」と。みんな自分で造作をやっている人が多くてプロ並みの工具が揃っています。木材なんかも言えばもらえそうな感じです。六甲山に住んでいる人同士は一体感があって、お店や公共サービスも限られているので「お互いさま」でやっていこうっていう気持ちがありますね。それに、近くに六甲山クリエイティブラボが開所したので、どんなところか見て来ました。六甲山に住んでいる神戸芸工大の先生が中心になって作った、誰でも安価で木材加工の工具や旋盤を使うことができる木工作業ラボです。オープニングイベントには六甲山材のコースター作りや、レンガ釜で焼いたピザのふるまいもありました。そういう場所も活用していけたらいいですね。

――最近だと、山でどんな方に出会いましたか?
松本:2ヶ月に一回くらい山の住民同士が持ち寄りでご飯会をやっているそうで、僕らも近所の人から誘われたり、道を歩いているときに「今日の夜にやるから」と声をかけてもらったりして参加しました。誰かのお家の庭に集まることもあるし、山の中の広場で集まることもあります。びっくりする程、人がいて毎回80人くらいは集まっています。お料理が得意な方が多いのか、食べ切れないくらい品数があって、ときには猟師さんがジビエをふるまってくれたり、飼っている鳥をさばいてくれたりもします。外国出身の方や、海外で働いていた人も結構いて、気が付けば英語が飛び交っているので、それもまたびっくりです。先日も軽トラックからバイオリンがでてきて、いきなり森のなかで演奏会が始まったりして、驚いてばかりです。

これからも、まだ知らない道を探して
――子どもさんの小学校は6年間ですが、その先についてもイメージがありますか?
松本:まだ全然わからないです(笑)行ってみたい中学校があれば、それに併せて山を下りるかもしれませんし。でも、最初に言ったみたいに、面白いと思ったほうに行くんだと思います。最近、台湾に旅行して気づいたんですが、なぜか細い狭い、その奥に何があるかわからないような小道に惹かれて入ってしまうんです。台湾はそんな小道が多くて。それでなぜかな?と思ったら僕は神戸の長田区生まれなんですね。長田区ってそんな小道がいっぱいあって、小道の奥に友だちが住んでいたり、遊ぶときも知らない路地を駆け回ったりしていた記憶があって。そういう場所に気持ちが動くというか、なんというか。だから六甲山の暮らしもそうですけど、まだ知らない歩いたことのない面白そうな道や出会いを、これからもどんどん選んでいくと思っています。

(コラム執筆・写真=東 善仁)